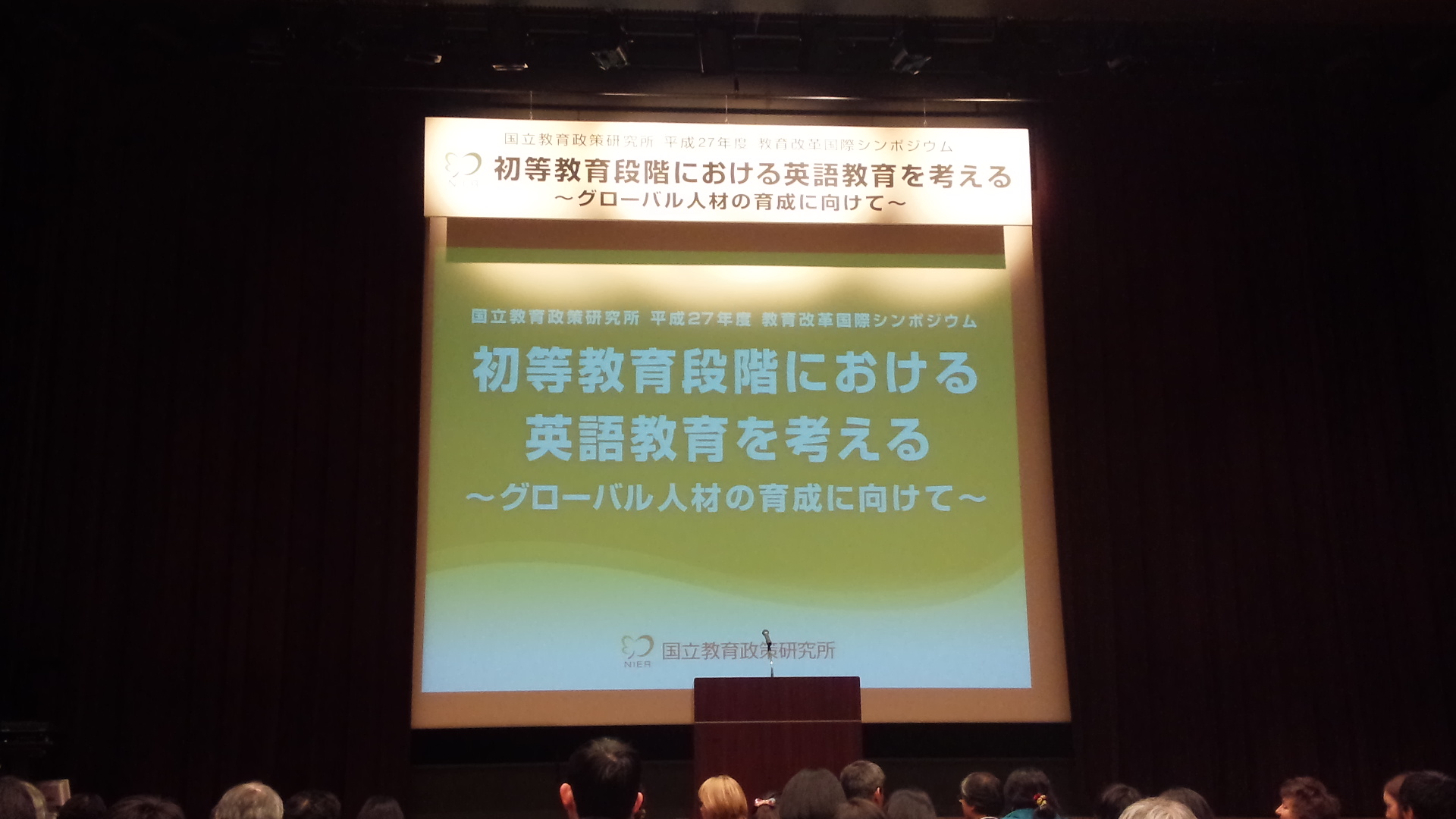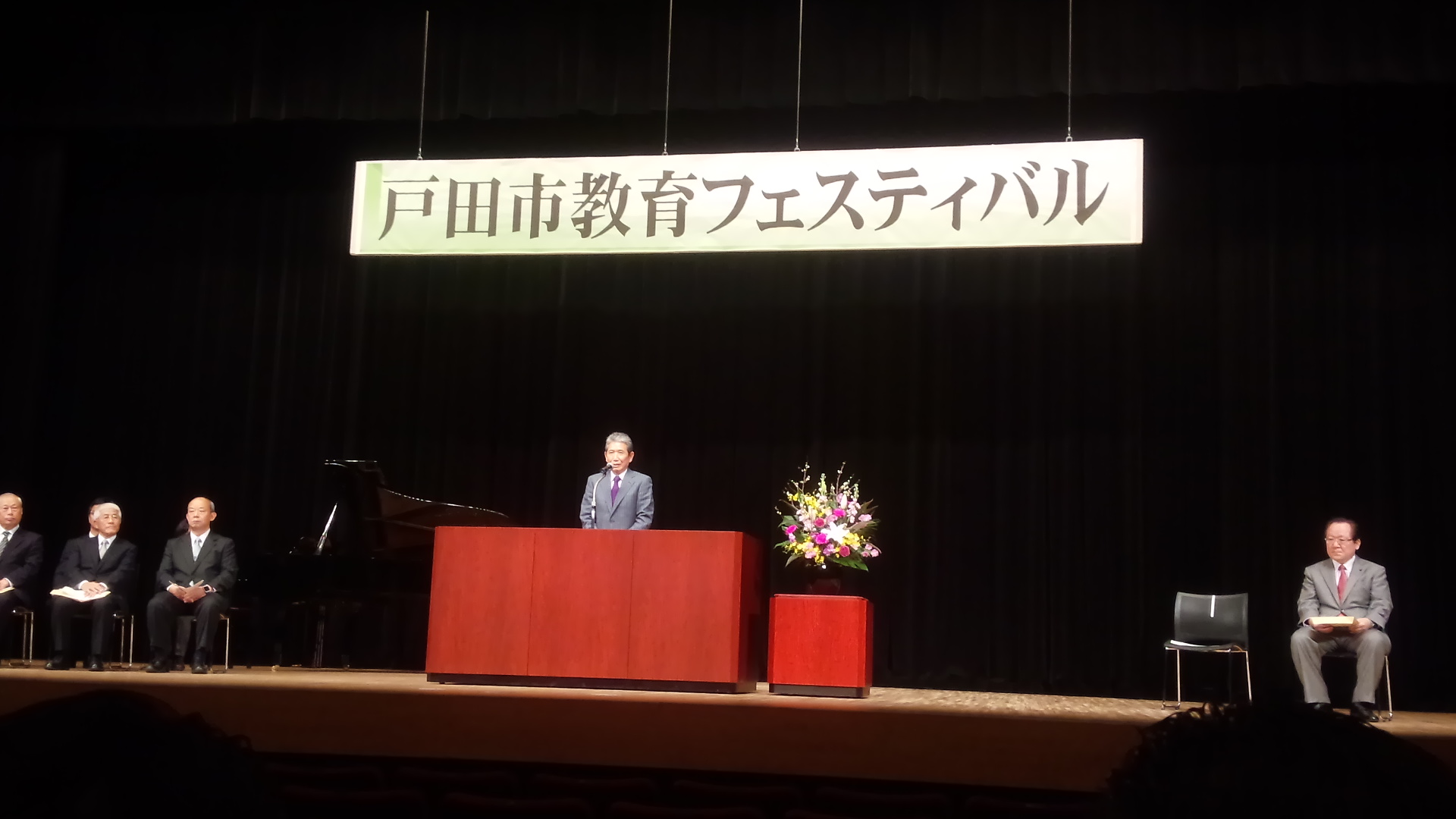[教育, 福祉と医療]2016年2月14日(日)

土曜日にスポーツセンターで開催された「第2回 戸田市ウィルチェアーラグビーフェスタ」に参加しました。
昨年に開かれた第1回の評判を伺って以来、ぜひ生で観てみたいと思っていました。
パラリンピック強化選手などによるデモンストレーションでは、車いす同士が激しくぶつかり合うダイナミックさと、団体球技特有のゲーム性に魅了され、純粋に観て楽しみした。
また今回は、国庫補助金をもとに戸田市が実施している「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」の一環として、市内小中学校の希望者に対する体験会も開かれました。

私も競技用の車いすに乗らせていただき、同じく参加していた同僚議員の車いすと激しくぶつかり合うことで、お互いに日頃のストレスを発散させました。
先日こちらでご報告した「ボッチャ」も、戸田市の新たなインクルーシブ教育(=障害のある者と障害のない者が共に学ぶ教育)の一環として授業に導入されたものですが、このように実際に見たり体験したりすることで、障害者スポーツへの興味や障害者に対する理解が一気に進みます。
障害者スポーツを通して小中学生の「心のバリアフリー」を推進する素晴らしい事業だと思います。
◎障害者スポーツの「ボッチャ」を見学(真木大輔公式ブログ)
◎「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」に関する平成27年9月議会での質疑(真木大輔公式サイト)
◇Facebookの元記事はこちら
[教育]2016年2月11日(木)

2月議会の補正予算案に計上された、来年度の「ALT派遣業務手数料 (約4500万円)」について、質疑を行いました。
戸田市は全国に先駆けて、平成14年度から全小中校へのALT配置を実施していますが、その雇用形態は、
小学校:業務委託→一部派遣→直接雇用→来年度は派遣
中学校:直接雇用→業務委託→一部派遣→直接雇用(来年度も直接雇用)
と、数年おきに変更されております。
そこで、議場では以下の質疑を行いました。
Q.
来年度の小学校のALTを派遣とする理由は?
A.
①ALTを直接雇用する自治体が増加していることで、戸田市が質の高いALTを直接雇用で確保することが困難になったため。
②ALTが年度途中で退職してしまい、代替ALTの確保が困難な場合、ALTの授業に穴を空けてしまうため。
【②の補足】
ALTの年度途中退職の状況は、H25年度1名、H26年度1名、H27年度3名となっており、実際に、H27年度は市内のある小学校で約1ヵ月の穴が空きました。(これについては、私も保護者の方からご意見を頂いており、担当課に聞き取りを行っていました。)
Q.
これまで雇用形態の変更が続いているが、今後は小学校のALTについて派遣で通していくつもりか?
A.
その通り。
ALTを直接雇用するか派遣にするかについては、どちらにもメリットとデメリットがありますが、雇用形態を数年おきに変更している現状は望ましいものとは言えません。
そこで質疑において、来年度に派遣へ変更となる小学校ALTについては、また数年後に直接雇用に戻すのではなく、今後一貫して派遣としていく意向を持っているかどうかを確認しました。
(なお、小学校ALTの雇用形態がここ数年で「派遣→直接雇用→派遣」と変更されている背景には、おそらく労働派遣法の改正があります。)
私は、質の高いALTであれば、直接雇用することで戸田市に囲っておくべきであると思います。
直接雇用のALTは、地域密着型である方が多く、雇用の継続性も期待できるため、高い教育効果が見込まれます。また、ALTにとっても、労働条件が良く、また市非常勤職員というステータスが得られるため、モチベーションのアップにつながります。
しかし、質の高いALTの確保は決して容易なものではないのも事実であり、また、新しい学習指導要領の実施により、今後小学校の英語の授業時間数が大幅に増加することからも、小学校ALTを派遣とし、一方で、指導内容の程度が高い中学校のALTを直接雇用のままとすることは、現実的な対応の一つと考えます。
少なくとも、戸田市のALTの雇用形態については、いまだ試行錯誤の時期にあるということが言えると思います。(とはいえ、他自治体に先んじた対応はとっています。)
「英語のまち戸田」の実現に向けて、ALTは重要な役割を担っています。
一昨年の3月議会で指摘した「中学校でのALTの活用」に加え、「ALTの雇用形態」についても、今後注視していきたいと思います。
◇Facebookの元記事はこちら
[教育]2016年2月8日(月)

先日の2月議会に提出された補正予算案に計上されていた「補習授業業務委託料(約1200万円)」について、議場で質疑を行いました。
答弁によると、既存の「とだっ子学習クラブ」を民間業者(塾)に委託し、活性化と充実を図る事業とのことです。
来年度から全中学校において、中1と中3は「夏休み」、中2は「通年」での補習授業が実施され、教科は「数学」と「英語」とのことです。
実際に補習授業の中身を見てみないと何とも言えない部分はありますが、現時点で評価できる点は、
●これまで学校によって実施状況がまちまちだった中学校のとだっ子学習クラブをしっかりと事業化する点。
●民間業者(塾)による効果的な授業が期待できる点。
●数学だけでなく英語も実施する点。
特に、最後の点については、市内で教育に携わる方から
「中学英語で落ちこぼれる生徒が多い」
「(小学校の)とだっ子学習クラブでは算数しか扱わない」
とのご意見を頂いていたので、それらの課題が今後はある程度解消されると思います。
近年、戸田市は民間業者(塾)との連携や業務委託を進めており、それは「効果的な授業」という点で大変優れています。
しかし、一定の事業費が掛かるものである以上、やはり「先生1:生徒多」の関係は変わらないのかなと思います。
勉強につまづいている子供達に対しては特に、「先生1:生徒1」に近い形で、(先生から与えられる課題ではなく)子供の分からないところを中心に、子供の理解のペースに合わせて教えてあげられることが理想です。
その点で、地域のボランティアの方々の手をお借りすることができれば大変ありがたいわけです。
来年度から実施される民間業者の補習授業に期待する一方で、このようなボランティア人材による「学びのセーフティネット」の場の提供について、今後も議会等で求めていきたいと思います。
◇Facebookの元記事はこちら
[教育]2016年1月20日(水)
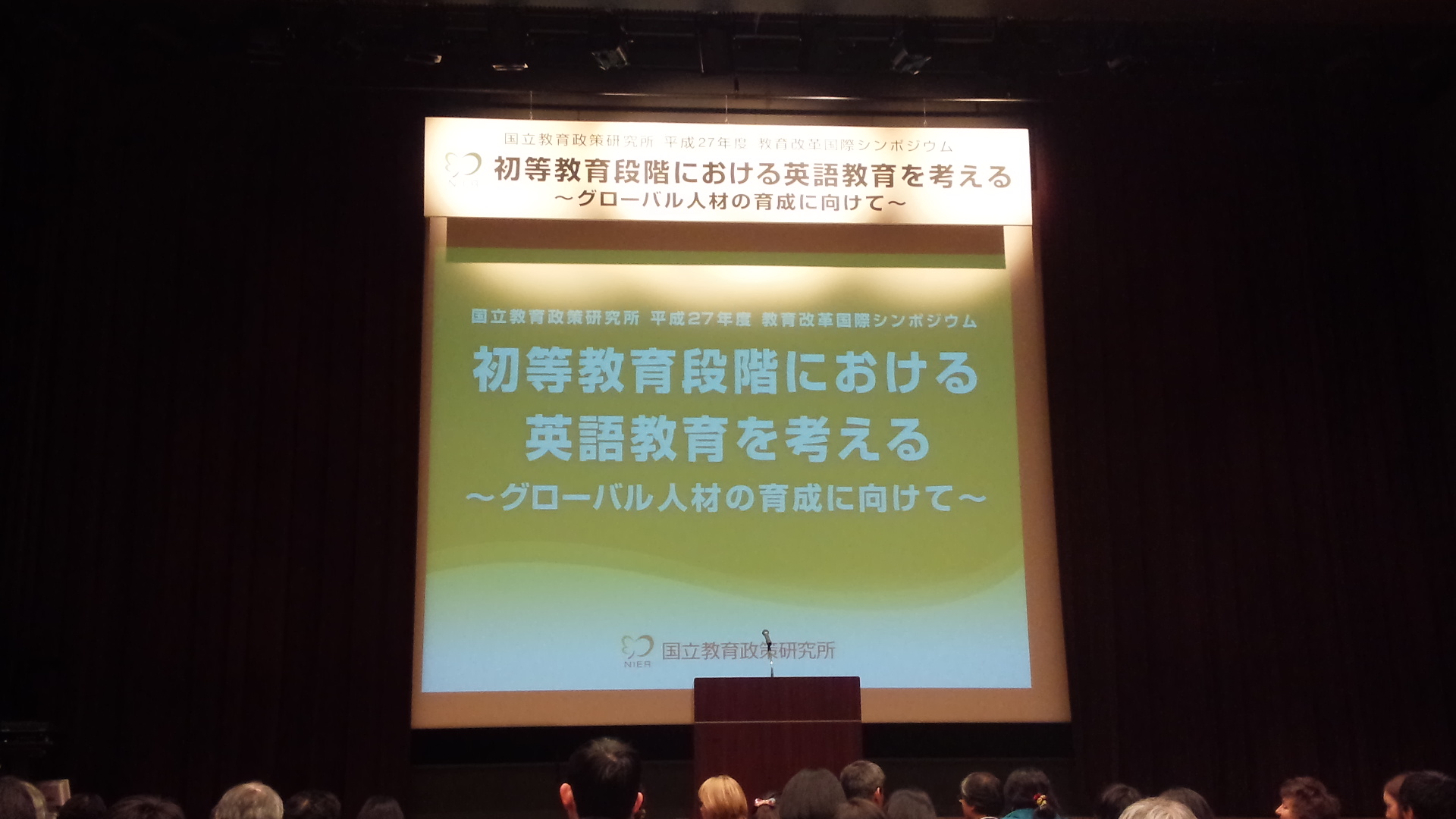
昨日は、文部科学省で開催された「平成27年度 教育改革国際シンポジウム」に参加しました。(私にとっては文科省への初めての訪問で心が躍りました。)
シンポジウムのテーマは、「英語教育」です。
先日の戸田市での研究会に関しては、今後の日本の英語教育の方針が「英語というツールを通してコミュニケーションを学ぶ」ものに転換してくこと、戸田市が既にその方針を見据えて教育改革を行っていることをお伝えしました。(※以下リンク参照)
今回のシンポジウムでは、その方針を進めていくうえで、日本人が変えなければいけない英語教育への考え方に関する指摘がありました。
私の目からウロコが落ちました。
そのいくつかを紹介します。
《目指すべき英語像について》
●日本人の学力は世界一だが、英語の能力は低い。
●日本人(子供も大人も)の、英語の有益性や必要性の認識は年々高まっている一方で、英語に対する自信は年々減少している。
●目指すべきは、「流暢な英語」ではなくて「万人に通じる英語」。
●実際に、非ネイティブスピーカーによる「通じる英語」に多く触れるほど、子供達の英語への自信が付くという実験結果がある。
●子供達は、流暢な英語を話すネイティブスピーカーではなく、通じる英語を話す非ネイティブスピーカーを心の中のモデルにしている。
●日本人英語教員が、「通じる英語」で積極的にコミュニケーションをとる姿を子供たちに見せることが、子供たちの英語を話す気持ちを高める。(まずは、日本人英語教員がグローバル化すべき。)
《ALTについて》
●子供にとって良い先生は、英語を流暢に話せる人ではなく、子供の心を拾ってあげられる人。
●ALTは欧米人などのネイティブスピーカーであるべきとの固定観念があるが、フィリピン人などの非ネイティブスピーカーには在日年数が長い人が多く、子供にとっての良いALTであることが多い。
●世界で英語を話す人の3分の2が、非ネイティブスピーカー。
《カリキュラム、指導法について》
●これまでは文法事項ありきだったが、これからは、小中高での一貫したCAN‐DO(=何ができるか)リストを作り、後からそこに適する文法事項を入れていくべき。(例文に使われている文法事項をすべて教える必要はなく、はじめは慣用句として扱って良い。)
●これからの英語授業では、「子供‐子供」間や「子供‐先生」間でのinteractionを中心とすべき。
最後に蛇足ですが、私は教育に関するシンポジウムに参加することが多いです。それは、教育について傲慢になることの危うさを認識しているためです。
「教育は誰でも語れる」と云われますが、政治家が安易にそれをしてしまうと、教育行政を歪ませる結果になることだってあります。子供達の将来に大きく関わることなので、無責任にそういうことはできません。
◎平成27年度 教育改革国際シンポジウム(国立教育政策研究所)
※後日、配布資料と講演録が掲載されます。
◎英語というツールを通してコミュニケーションを学ぶ(真木大輔公式ブログ)
◇Facebookの元記事はこちら
[教育]2016年1月9日(土)
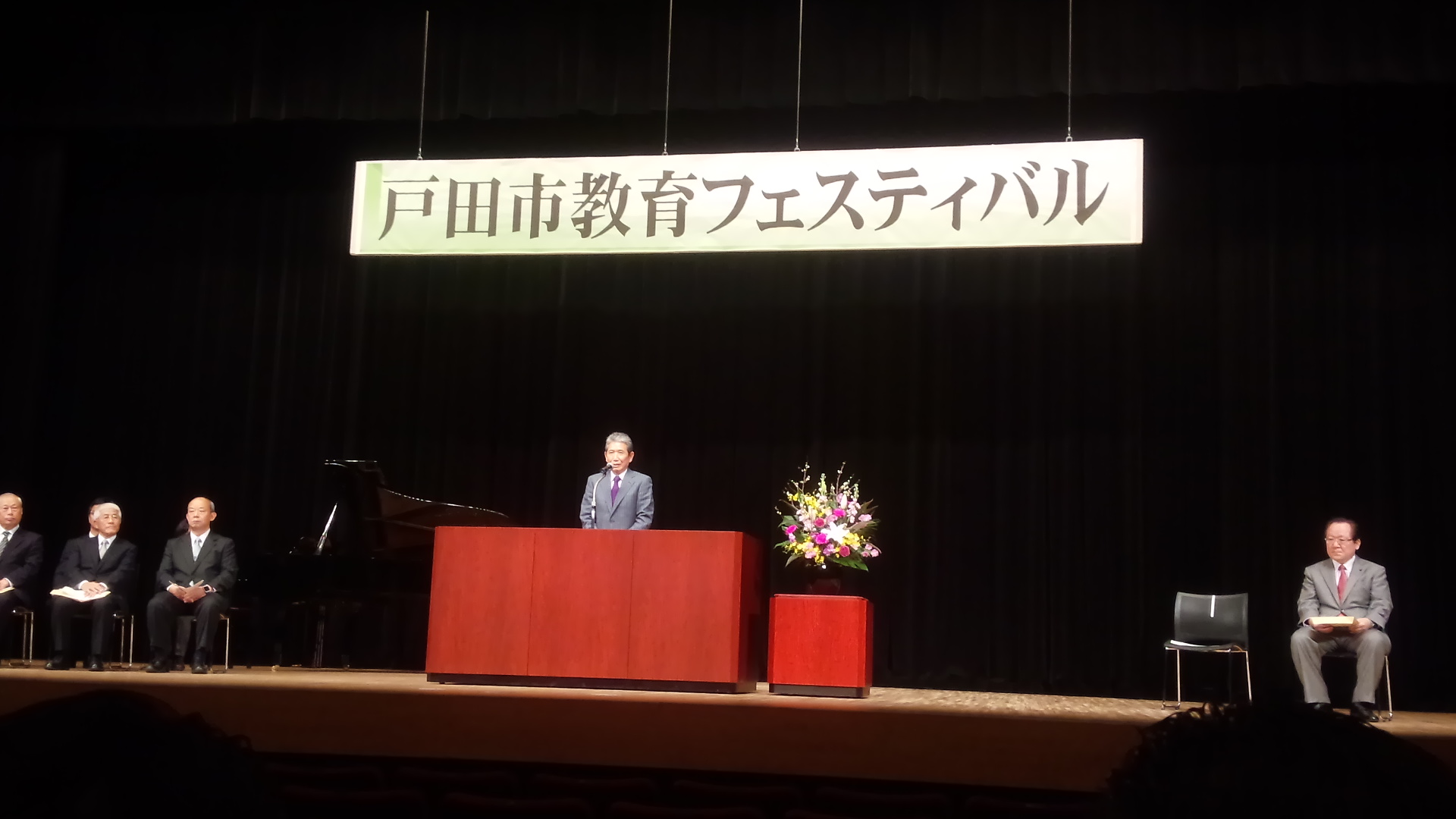
●昨日は、「戸田市教育フェスティバル」に参加しました。
毎年1月に戸田市の教職員が一同に会し、教育の最新テーマに関する講演が行われる貴重な場です。
今回の講演は、以下の3つでした。
①文科省による、「アクティブラーニング」についての講演
②ベネッセによる、戸田市との包括協定についての講演
③森塾による、成績を上げる授業のコツについての講演
特に、①の講演が印象的でした。
新しい学習指導要領の中心に据えられる「アクティブラーニング」の第一人者である田村学氏による講演だったのですが、アクティブラーニングが必要とされている背景やその効果、授業の工夫などについて非常にわかりやすく説明をされました。
これまでの学習では、授業から「インプット」したものをテストで「アウトプット」することが中心でした。
これからの学習(アクティブラーニング)では、授業以外にも、本やネット、クラスメートから「インプット」したものを、テストだけでなくネットやクラスメートにも「アウトプット」し、その過程のなかでクラスメートとの相互作用によってよりクリエイティブな答えを導き出す、という作業が行われていきます。
このような学習によって、これからの子供達は、社会で必要とされるスキルを学校で身に付け、(日本国内にも増えるであろう)各国の人材と渡り合うことができるようになるわけです。
●新たな考え方が浸透するには時間が掛かるものですが、戸田市は、数年前からこのような「新しい学び」に取り組んでおり、市内各校の学校だよりに目を通しても、次第に校長先生方へ「アクティブラーニング」への理解が拡がっているように感じます。
今回の教育フェスティバルは、それが現場にいる先生方にも共有される素晴らしい機会だったと思います。
次期学習指導要領が実施されると、全国の学校でアクティブラーニングが展開されるわけですが、おそらく自治体によってバラつきが出てくるのではないかと私は考えています。
それこそ、アクティブラーニングは、“アクティブ(主体的)”に実践していってこそ、その心が理解できていくものであって、あとから形だけを真似てうまくいく性質のものではないと思います。
●さて、戸田市の教育行政の今後4年間の計画である「第3次 戸田市教育振興計画」の案が完成し、先週からパブリックコメントが実施されています。
上述のアクティブラーニングなどの国の方向性を先取りした施策や、戸田市のいまの課題に対応する施策が多く盛り込まれ、4年前の計画から大幅にアップデートされています。
計画案の内容やそれに対するご意見の送付は、以下のリンク先からどうぞ。
◎第3次戸田市教育振興計画(案)についての意見募集(戸田市公式サイト)
◇Facebookの元記事はこちら